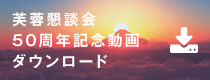エフニュース
「住江織物株式会社」から新社名「SUMINOE株式会社」に変更のお知らせ
 2024年12月2日、住江織物株式会社はSUMINOE株式会社に社名変更しました。
2024年12月2日、住江織物株式会社はSUMINOE株式会社に社名変更しました。
明治の創業以来、私たちは新しい空間づくりに挑戦してきました。日本初の絨毯も、環境にやさしいリサイクルカーペットも、自動車や鉄道などの移動空間の内装も、これまでにない空間づくりのため、常に自分たちを超え続けてきました。
そしていま、私たちはこれまで積み重ねてきた技術を力に、貢献する空間の領域をさらに広げていこうとしています。進取の気風はそのままに、めざす理想はもっと柔軟に、もっと先へ。
「あらゆる空間に、イノベーションを。」。このタグラインの想いを世界中に広げていくため、SUMINOEは新たな空間の創造へ走り続けます。
新社長ご紹介
このほどご就任された新社長のプロフィールをご紹介いたします。
*発行日(3月25日)時点の役職名を記載しています。
東京建物株式会社 代表取締役 社長執行役員 小澤 克人(おざわ かつひと)氏

- 就任日
- 令和7年1月1日
- 就任にあたっての抱負
- 当社は2030年を見据えた長期ビジョン「次世代デベロッパーへ」の実現に向け 着実に歩みを進めています。社員一人ひとりが力を最大限に発揮できる企業文化を育み、持続的な企業価値向上を実現することで、社会に必要とされる会社であり続けられるよう取り組んでまいります。
- 好きな言葉・信条
- 「満は損を招き、謙は益を受く」
- 趣 味
- ゴルフ、旅行
- 出身地/年齢
- 神奈川県/61歳
東京建物不動産販売株式会社 代表取締役 社長執行役員 菅谷 健二(すがや けんじ)氏

- 就任日
- 令和7年1月1日
- 就任にあたっての抱負
- 本年、当社は設立45周年を迎えるとともに、東京建物グループの新たな中期経営計画が始動します。「信頼・創造・未来」という企業理念の下、仲介事業・アセット ソリューション事業・賃貸事業を通じ、将来に亘って不動産の付加価値を創造し、お客様のニーズにお応えしてまいります。
- 好きな言葉・信条
- 「一隅を照らす」
- 趣 味
- 料理、水泳、愛犬
- 出身地/年齢
- 千葉県/56歳
エフ短信
第36回芙蓉懇談会社長懇親会開催
2024年11月29日に、パレスホテル東京において社長懇親会が開催されました。みずほ信託銀行の笹田社長のご挨拶に続き、レゾナック・ホールディングスの髙橋社長のご発声で乾杯しました。その後、初参加の8名からご挨拶がありました。
会場にはたくさんの歓談の輪ができ、話に花が咲いていました。
-

みずほ信託銀行
笹田社長 -

レゾナック・
ホールディングス
髙橋社長 
代表委員会懇親会開催
11月21日、パレスホテル東京に33名の代表委員が集まり懇親会が開催されました。みずほフィナンシャルグループの武取締役代表執行役副社長による開会のご挨拶に続き、沖電気工業の寺本代表取締役副社長の乾杯で会は賑やかに始まりました。初参加者も楽しいご挨拶ですっかり場に溶け込んでいました。参加者は和気あいあいと時間を過ごされました。
-

みずほフィナンシャル
グループ
武副社長 
沖電気工業
寺本副社長
実行委員会新年会賀詞交換会開催
1月20日、コートヤード・マリオット 銀座東武ホテルで実行委員会新年会賀詞交換会が開催されました。みずほ信託銀行法人業務部の土田部付部長の開会のご挨拶に続き、損害保険ジャパン企業営業支援部の島谷リーダーの乾杯の発声で、会場は一気に和やかな雰囲気に包まれました。約60名の実行委員は、みな笑顔で親睦を深めていました。
-

みずほ信託銀行
土田部付部長 -

損害保険ジャパン
島谷リーダー 
第39回芙蓉グループ剣道大会開催
第39回芙蓉グループ剣道大会は10月20日、丸紅多摩研修センターにおいて、大会会長に明治安田生命保険・伊藤俊氏(剣道部監督)、審判長に全日本剣道連盟相談役・福本修二範士八段をお迎えし、11社より約100名の参加のもと開催され、剣道を通じて各社の親睦を深め合いました。
今年度から各社OBを含めた高壮年紅白戦を再開し、盛り上がりをみせました。男子個人戦は山中選手(レゾナック)、女子個人戦は高岡選手(キヤノン)、団体戦は丸紅Aチームとの接戦を制した、キヤノンAチームが優勝し、例年以上に盛況の大会となりました。
【団体戦】 優 勝 キヤノン Aチーム
準優勝 丸紅 Aチーム
第3位 みずほFG Aチーム/SOMPOホールディングス
-

個人戦優勝の山中選手(右)
と高岡選手 -

団体戦優勝のキヤノンAチーム
マニラ芙蓉会第81回ゴルフコンペ開催
11月30日、Canlubang Golf & Country
Clubにおいて第81回マニラ芙蓉会ゴルフコンペを開催しました。
17社34名とたくさんの参加者が集まるなか、天候にも恵まれ、日ごろの鍛錬の成果を競い合う場として大いに盛り上がりました。表彰式後の懇親会も会員同士の交流を深める貴重な機会となりました。
今後も懇親会、ゴルフコンペなどを定期的に開催し、会員同士の親睦を深めていく予定です。
台湾芙蓉懇談会勉強会・第101回ゴルフコンペ開催
12月12日、清華大学の小笠原欣幸教授からトランプ新政権の影響も含めた今後の台湾情勢につきご講演いただきました。台湾政治研究に長年携わってこられ、通常とは異なる切り口・視点からの大変示唆に富むお話で、会員企業から非常に好評でした。
また同14日には101回目となるゴルフコンペを高雄で開催しました。新メンバーも加わり、レベルの高いゴルフとなりました。
未加入のF会企業の方は台湾丸紅まで是非ご連絡ください。
シンガポール芙蓉会懇親会開催
1月13日に、みずほ銀行シンガポール支店内「MIZUHOME」において24年度2回目のシンガポール芙蓉会懇親会を開催いたしました。
年始での開催にふさわしく、みずほ銀行産業調査部アジア室の田村優衣エコノミストより「2025年のアジア経済政治情勢」をご講演いただきました。
今回も24社49名と多くの方々にご参加いただき、各社ビジネスの相互理解、会員同士の親睦を深める場としておおいに盛り上がりました。
今後もグループ内ネットワーキング推進の一環として、定期的な開催を予定しています。
芙蓉情報システム懇談会10月例会開催
10月18日、井関農機松山製作所見学会が開催されました。
伝統的な工法により鋳物や歯車が製造される様子から、コンピューター制御されたロボットによりトラクターが組み立てられる製造過程まで見学しました。また最新型の大型トラクターやコンバインの運転席に座ることで、スマート農業を実感することができました。これからも情報システムが活用されているあらゆる業種や産業に触れてみたいと思います。
芙蓉環境ビジネス協議会11月例会開催
11月1日に、「室蘭市水素サプライチェーン実証事業」および「五洋建設室蘭製作所」見学会を開催しました。
室蘭市は、風力発電所で発電した電力の一部を使って水素を製造しています。この水素を円筒形のタンクに詰めて輸送し、道の駅などの施設で利用しています。製造施設、利用施設の両面から水素を活用するシステムを見学しました。
五洋建設室蘭製作所は、太陽光発電と水素発電で稼働する再生エネ100%工場です。洋上風力建設関連の仮設鋼構造物を製作している様子を見ることができました。
将来を見据えた2つの取り組みに触れ、室蘭市では環境にやさしい社会の仕組みづくりが着々と進んでいることを知ることができました。
芙蓉研究開発懇談会11月例会開催
11月8日に「鶴岡サイエンスパーク」見学会を開催しました。
当日は鶴岡サイエンスパーク代表理事で慶應義塾大学名誉教授の冨田勝氏からお話をいただきました。鶴岡に産業を興そうという強い想いに対し、慶應義塾大学が協力する形でプロジェクトが進められた経緯や、これまでに多くの成果があったことなどをご説明いただきました。また事業化に成功した2社からのプレゼンもありました。
鶴岡サイエンスパークは、宿泊滞在施設「SUIDEN
TERRASSE」などと一体となり、地域をつなぐコミュニティの場を形成していることも知りました。地域振興の1つの在り方を見た思いがしました。

-

冨田氏(中央)とご参加のみなさん
芙蓉情報システム懇談会11月例会開催
11月18日、丸紅本社ビルで講演会が開催されました。芙蓉情報システム懇談会はじめ他の専門部会会員含め約60名がリアルとオンラインで集まりました。講師はみずほリサーチ&テクノロジーズ(株)デジタルコンサルティング部シニアコンサルタントの木村俊介氏、テーマは「生成AIがもたらしたインパクトとビジネス変革の現在地」でした。
生成AIとは何か、生成AIが躍進した経緯などを振り返るとともに、国内の活用事例など幅広く解説いただきました。一方で生成AIを活用するための課題も多く、人材育成やデータ整備が必要との指摘がありました。生成AIと上手く付き合うための情報を得ることができました。


木村氏
芙蓉環境ビジネス協議会12月例会開催
12月2日、「クリーンプラザふじみ」見学会が開催されました。
「クリーンプラザふじみ」には三鷹市と調布市約40万市民の燃やせるゴミが集められます。大量のごみを最新設備で処理し、騒音対策やにおい対策が徹底されていることを体感することができました。またJFEエンジニアリングと協働しておこなわれているCO2分離回収・液化実証実験の現場を視察し、先進的な取組みが行われていることを知ることができました。